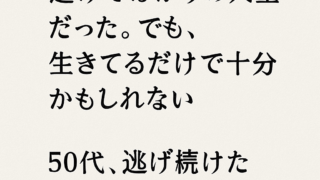コンビニに寄る理由が思いつかなかった
退社の瞬間
ビルの出口で自動ドアが開いた瞬間、眼鏡が少し曇った。
外気と室温のわずかな差。
指先でフレームを押し上げ、歩道の端に立つ。
パソコンのファンの音が、まだ耳の奥に残っている気がした。
確かめる術は、もうない。
鞄の重みを肩に預け直し、
駅とは逆方向にあるコンビニの看板を見つめた。
歩き始める
夜の街で、そこだけが過剰に白い。
吸い寄せられるように足が向く。
入り口のマットを踏む前に、ふと足が止まった。
何か買うものはあっただろうか。
卵はある。牛乳も半分残っている。
酒を飲みたい気分でもないし、甘いものが欲しいわけでもない。
ただ、この明るい光の中に、
数分間だけ身を置きたい。
それだけの欲求だった。
考えが勝手に浮かぶ
もし今、店に入って、何も買わずに出たら。
あるいは、必要のないものを一つ買ったら。
それは、何かの埋め合わせになるのだろうか。
「まっすぐ帰りたくない」
その気持ちの正体を探ろうとするが、
思考は滑って、うまく掴めない。
仕事でミスをしたわけではない。
誰かに叱責されたわけでもない。
ただ、今日という一日を、
何の変化もなく「完了」させてしまうことに、
身体がわずかに抵抗している。
自動ドアのセンサーが、
私を検知しようと、カチリと音を立てた。
答えを出さずに終わる
結局、ドアが開く前に背を向けた。
寄る理由は、どうしても思いつかなかった。
数歩歩くと、背後の白い光は遠ざかり、
いつもの薄暗い帰り道に戻る。
コンビニに寄っても、寄らなくても、
家に辿り着く時間は、ほとんど変わらない。
明日の朝になれば、
今日コンビニに寄らなかったことなど、
きっと思い出しもしない。
今はただ、
重い鞄を揺らしながら歩く。
それだけだった。