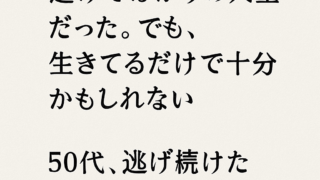今日も、誰にも会わなかった
退社の瞬間
タイムカードを切る。
ガチャン、という無機質な音が、指先から腕に伝わった。
それだけで、僕の「社会的な役割」は終わるはずだった。
パソコンの電源を落とし、デスクの隅に溜まったわずかな埃を指でなぞる。
「お疲れ様でした」
誰に言うでもなく、小さな声が喉の奥で消えた。
事務所を出るとき、同僚の後ろ姿が見えたけれど、あえて歩幅を緩めた。
今は、言葉を交わすためのエネルギーが、一滴も残っていない。
歩き始める
外に出ると、夜の空気が肺の奥まで入り込んできた。
会社という四角い箱の中から、夜の街というあわいの境界へ。
駅までの道、街灯の下を歩く自分の影が、伸びたり縮んだりするのを眺める。
すれ違う人は皆、それぞれの目的地に向かって急いでいる。
イヤホンを耳に押し込み、スマートフォンの画面を見つめ、どこか別の場所に意識を飛ばしている。
僕もその一人だ。
誰かと視線が合うことも、肩が触れ合うこともない。
考えが勝手に浮かぶ
ふと、今日一日の出来事が、泥のように頭の底に沈殿しているのを感じる。
あそこで言い返すべきだったのか。
あの作業は、本当にあれで正解だったのか。
仕事は終わったはずなのに、終わった感じがしない。
未処理の感情が、肩にかけたリュックの重さとして残っている。
駅のホームで電車を待つ間、自動販売機の明かりを見つめる。
何を飲みたいわけでもない。
ただ、光を眺めている。
家が近づく
ふとした瞬間に、「これでいいのだろうか」という問いが浮かんでは消える。
後悔ではない。
かといって、希望でもない。
ただ、何かが足りないような、あるいは何かが多すぎるような、言葉にならない違和感。
電車に揺られ、最寄り駅の改札を抜ける。
住宅街に入ると、さらに音は消えた。
どこの家からも、夕飯の匂いやテレビの音が漏れてこない。
自分の足音だけが、コンクリートに反響している。
それだけ
アパートの階段を上り、見慣れたドアの前に立つ。
ポケットを探り、冷たい鍵を鍵穴に差し込む。
このドアを開ければ、今日という日は終わる。
それでいいのかどうかは、まだ考えない。
▶ 関連記事 → 誰もいない公園のベンチで|50代、独りから始まる物語 第5話