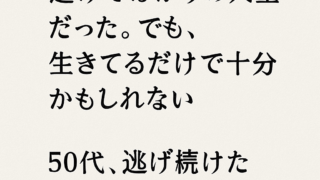🚶♂️ 帰り道に、ふと立ち止まった
仕事帰りの夜、風が冷たかった。
秋の終わり。街の空気には、冬の気配が静かに混じりはじめている。
会社の門を出た瞬間、首筋を撫でた風が、
一日の疲れを思い出させるようだった。
ペダルを漕ぐ気にもなれず、自転車を押して歩いた。
街の明かりは遠く、歩道を行き交う人たちは、
みんな急ぎ足でどこかへ帰っていく。
その中で、自分だけが取り残されているような気がした。
ふと、横断歩道の向こうに白い光が浮かんでいた。
コンビニ。
いつもなら素通りするだけの店なのに、
その夜はなぜか、やけにあたたかく見えた。
あの白い灯りの中には、
きっと「何も考えずにいられる時間」がある気がした。
「寄るつもりなかったんだけどな」
つぶやきながら、自動ドアの音に吸い込まれた。
🏪 灯りの中で、少しだけ息をついた
――ピンポーン。
ドアが開く音と同時に、外気とは違うぬるい空気が包み込んだ。
おでんの湯気。コーヒーマシンの蒸気。
そして、冷蔵棚から漂うわずかな冷気。
それらが混ざり合って、奇妙に落ち着く匂いがした。
「いらっしゃいませ」
マスク越しの声。けれど、どこかやさしかった。
この“何気なさ”が、今の自分には必要だった。
缶コーヒーを取ろうと冷蔵ケースを開けると、
指先に冷たい金属の感触が伝わる。
この冷たさが、
逆に“生きている実感”のように感じられた。
隣の棚では、スーツ姿の男性が夕食を選んでいる。
その横で、学生らしき青年がスマホを見ながらパンを手に取る。
誰も特別なことはしていない。
ただ「生きるための買い物」をしているだけだ。
それなのに、その普通の光景が、
涙が出るほど尊く思えた。
☕ 「おつかれさまです」の一言が沁みた
レジに並ぶと、若い店員が会釈をした。
まだ二十歳そこそこのような青年。
その彼が差し出した温かい缶コーヒーを受け取った瞬間、
ぽつりと声が落ちた。
「おつかれさまです。」
その一言が、胸の奥で静かに弾けた。
たった五文字。
けれど、この夜の自分にとっては、
まるで「よく頑張ったね」と言われたようだった。
「ありがとう」
気づけば口からこぼれていた。
声は弱く、震えていたけれど、
それでも、言葉を返すことができた自分に少しだけ救われた。
レジ横のビニール袋を断って、缶をそのまま受け取る。
手のひらに伝わるぬくもり。
それを握りしめたまま、
また夜の冷たい風の中へ戻っていった。
🌆 灯りの向こうに、人の気配があった
橋の手前で立ち止まる。
遠くの街の光が、川面に揺れていた。
コンビニの灯りと同じように、
その光のひとつひとつが、誰かの生活を照らしている。
今日、あの店に入らなければ、
誰かと目を合わせることもなかった。
会話もせずに一日が終わっていたかもしれない。
思えば、ここ最近そんな日ばかりだった。
人と話すことが減り、
気づけば“孤独”が日常の中に根を張っていた。
けれど、それでも――
あの一言で、何かが少しだけほぐれた気がした。
夜風が頬を撫でる。
街のざわめきと川の音が混ざって、
まるで遠くから流れてくる“優しいノイズ”のようだった。
🌙 小さなぬくもりが、明日をつなぐ
ポケットの中で、缶コーヒーはぬるくなっていた。
でも、冷めたその温度が不思議と心地よかった。
人の優しさも、たぶんこんなものなのかもしれない。
熱く燃えるようなものじゃなくて、
静かに、じんわりと沁みていく。
歩きながら、ふと立ち止まる。
「また、あの店に寄ろうかな」
そんな言葉が浮かんだ。
何かを求めているわけじゃない。
ただ、灯りの下で“誰かの声”を聞けるだけでいい。
見上げた空には、薄い雲の切れ間から月がのぞいていた。
光は弱いけれど、確かにそこにある。
まるで、自分の人生そのものみたいだと思った。
派手じゃない。けれど、まだ光っている。
家までの道を、少しだけゆっくり歩く。
この夜が終われば、また朝が来る。
同じ日々の繰り返しのようでいて、
たぶん今日の夜は、昨日とは少し違う。
🔸 小さな出口(今日の一歩)
ほんの一瞬でも、心が温まる場所がある。
それだけで、この夜は十分だと思えた。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
🪷 心の四季 ― シリーズ全体の地図
第1〜5話=心の冬(停滞・苦悩)/ 第6〜10話=心の春(癒し・受容・再出発)
この章の位置:第3話=「癒し(ほぐれる)」
心理の連なり:
停滞 → 苦悩 → 癒し → 受容 → 再出発 → 解放 → 再起 → 受容 → 安心
各話は独立しつつも、全体では「心の冬」から「心の春」へ滑らかに移行する構造です。
自分が今どの季節に近いかを感じながら読むと、物語がより自分ごととして響きます。